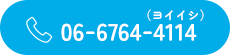健診で「異常あり」と
指摘された方へ
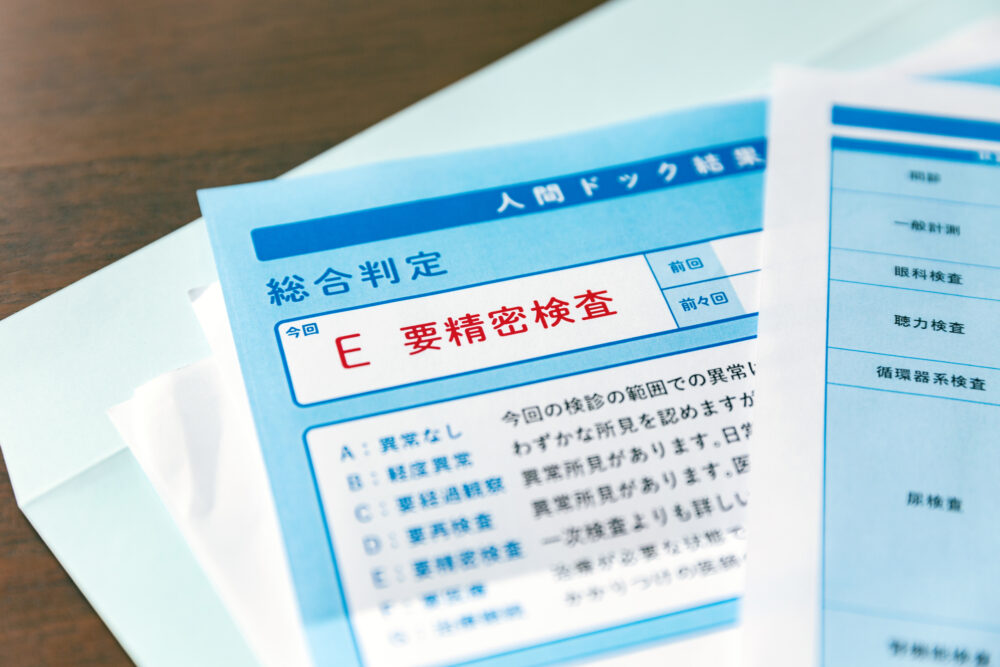 健康診断の結果に異常があった、つまり「要再検査」「要精密検査」「要治療」といった判定が出た場合には、まずは落ち着き、しかし放置せず、その判定に従った対応をとることが大切です。
健康診断の結果に異常があった、つまり「要再検査」「要精密検査」「要治療」といった判定が出た場合には、まずは落ち着き、しかし放置せず、その判定に従った対応をとることが大切です。
「忙しいから」と受診をしなかったり、後回しにしてしまうと、病気が発症・悪化することがあります。病気を早期発見・早期治療するため、必ず、お早目に受診してください。再検査・精密検査をして、実は問題がなかったというケースもあります。不要な心配をしないためにも、早期受診が重要です。
再検査・要精密検査・要治療の判定を受けた方は、鶴橋駅前よしかわ内科にご相談ください。
健康診断の結果からわかることや、再検査の重要性
再検査や精密検査は、健康診断の結果が正しいものであるかを確認するため、またより詳しく調べて病気を特定するために大切なものとなります。
異常なし
正常な範囲内に収まる結果であったため、特に問題はありません。しかし、何か自覚症状がある場合には、医療機関を受診するようにしましょう。
要再検査
何らかの病気である可能性、あるいは一時的な数値の変動が起こっていた可能性がある場合に、要再検査の判定がなされます。再度、同じ検査を行います。
要精密検査
何らかの病気である可能性を疑い、より詳しい検査が必要という判定です。どのような検査を行うかは、異常のあった項目によって変わってきます。
要治療
治療が必要という判定です。すぐに医療機関を受診し、正式な診断と治療を受けましょう。
健診で異常が出やすい検査項目とよくある指摘
健康診断では、主に以下のような項目についてリスクの判定が行われます。それぞれ、どのような状態であるのか、解説していきます。
高血圧
最高血圧または最低血圧が正常値を超えた状態です。血管に負荷がかかっている状態であるため、心筋梗塞や脳卒中などの発症リスクが高まります。
血糖値・HbA1c
血糖値とは、血液中のブドウ糖の濃度を示す数値です。HbA1cは、過去1~2ヶ月の血糖値の推移が反映された数値です。血糖値やHbA1cが高い場合、糖尿病の疑いが強まります。糖尿病の場合、心筋梗塞や脳卒中の発症リスク、網膜症・腎症・神経障害の発症リスクが高まります。
中性脂肪・コレステロール
中性脂肪やLDLコレステロールの値が高い、HDLコレステロールの値が低い場合には、脂質異常症の疑いが強まります。脂質異常症は、高血圧や糖尿病と同様に動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳卒中の発症リスクを高めます。
尿酸値
血中の尿酸の濃度を指します。尿酸値が一定の基準を超えると、高尿酸血症と診断されます。高尿酸血症の段階ではほぼ無症状ですが、放置していると関節の痛み・腫れを伴う痛風発作を招きます。また、尿路結石、心筋梗塞などの発症リスクも高まります。
尿糖・尿蛋白・尿潜血
尿糖、尿蛋白、尿潜血といった項目で異常がある場合には、尿路結石、腎機能障害、腎炎、糖尿病、尿路感染症などの病気を疑います。
メタボリックシンドローム
高血圧・血糖値・脂質のうち2つ以上で異常があり、かつ内臓脂肪型肥満が認められる状態です。高血圧・糖尿病・脂質異常症およびその合併症のリスクが高い状態であり、早急な治療が必要です。
肝機能
ビリルビンやAST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、ALPは肝臓の機能を示す項目です。正常域を超えている場合には、肝機能障害が疑われます。
貧血
血液検査における赤血球数、ヘモグロビン値、ヘマトクリット値の測定結果から、貧血の有無を判定します。貧血は、鉄分の不足、消化管の出血、婦人科疾患など、さまざまな原因によって生じます。
心電図
心電図検査で異常を指摘された場合には、不整脈、狭心症・心筋梗塞、心肥大などの病気を疑います。特にすでに息苦しさや胸痛が現れている場合には、早急な受診が必要です。
便潜血
便潜血検査で陽性だった場合、その便に血液が含まれていたということです。痔や消化管疾患を疑います。大腸がんなど命にかかわる疾患も疑われるため、精密検査として大腸カメラ検査が必要です。
胸部レントゲン検査での異常
異常を指摘された場合には、呼吸器や循環器の病気が疑われます。特に重大な病気としては、肺がんや心臓病、胸部大動脈瘤などが挙げられます。
胸部レントゲン検査について
 レントゲン検査(X線)は、X線という特殊な電磁波を使って体内の様子を画像化する検査方法です。X線は体内の組織によって通過しやすさが異なるという特性があります。そのため、X線が通過しやすい空洞は黒く、通過しにくい骨は白く映ります。
レントゲン検査(X線)は、X線という特殊な電磁波を使って体内の様子を画像化する検査方法です。X線は体内の組織によって通過しやすさが異なるという特性があります。そのため、X線が通過しやすい空洞は黒く、通過しにくい骨は白く映ります。
健康診断などで行われる胸部レントゲン検査では、背中側から胸部にX線を照射して、肺や心臓、縦隔(両肺の間にある部分)などの状態を調べます。レントゲン検査で使用する放射線はごくわずかですので、成人の健康にはほとんど影響はありません。比較的安全性の高い検査方法と言えます。
胸部レントゲン(X線)検査で
わかる病気
胸部レントゲン検査は、様々な胸部疾患の発見に役立ちます。この検査で確認できる疾患には以下のようなものがあります。
肺結核・肺炎
結核は結核菌による感染症です。肺に慢性的な炎症が起きて空洞が生じるため、レントゲン画像では肺の上部に影や結節状の病変として現れます。
肺炎は細菌やウイルスによる肺の急性炎症です。肺胞内に炎症や分泌物が溜まるため、レントゲンでは肺の白い影(浸潤影)として観察されます。
気管支炎などの肺の炎症
気管支炎は気管支に炎症が起こる疾患で、慢性化すると咳や痰が長期間続きます。レントゲンでは気管支の壁が厚くなったり、その周囲に影が現れたりすることがあります。
気管支の状態をより詳しく観察するには、別途CT検査による精密検査も検討します。
肺気腫
長期の喫煙などが原因で肺胞が破壊され、呼吸機能が低下する病気です。慢性閉塞性肺疾患(COPD)の一種でもあります。レントゲンでは肺が過度に膨張して見え、横隔膜が通常より低く映ります。
気胸
肺の一部が破れて空気が胸腔(肺と胸壁の間の空間)に漏れ出し、肺がしぼんでしまう状態です。レントゲンでは、肺が縮小してその周囲に空気の層が見られます。
若い痩せた男性に多く見られる自然気胸や、外傷による外傷性気胸などがあります。
胸膜炎
肺を包む薄い膜(胸膜)に炎症が生じる病気です。感染症や自己免疫疾患、がんなどが原因となります。炎症により胸水(胸腔内に溜まる液体)が生じることが多く、レントゲンでは下部が白く映ります。
肺線維症
肺の組織が硬くなる(線維化する)病気で、原因不明の特発性肺線維症や膠原病に伴うものなどがあります。レントゲンでは両側の肺に網目状の影(線維化像)が見られますが、初期には変化がわかりにくいことも多いです。
心臓病
心不全や弁膜症などの心臓病だと、レントゲンで心臓の拡大や肺うっ血が見られます。心不全が進行すると肺に水分が溜まり(肺水腫)、白い影として映し出されます。
心肥大
心臓の筋肉が厚くなった状態です。主に高血圧や心臓弁膜症などが原因となります。レントゲンでは心臓の影(心陰影)が通常より大きく見えます。
胸部大動脈瘤
動脈(心臓から出る最も太い動脈)の一部が異常に膨らむ病気です。レントゲンで胸部の異常な陰影や大動脈の拡張が見られる場合は、胸部大動脈瘤の可能性が考えられます。破裂すると命に関わる緊急事態となりますが、早期に発見できれば治療が可能です。