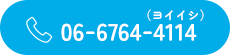気管支喘息(ぜんそく)について
 気管支喘息とは、呼吸時の空気の通り道である気管、気管支といった「気道」において、慢性的な炎症が生じる病気です。炎症によって気道が狭くなると、呼吸しづらさ、咳、喘鳴といった症状が引き起こされます。
気管支喘息とは、呼吸時の空気の通り道である気管、気管支といった「気道」において、慢性的な炎症が生じる病気です。炎症によって気道が狭くなると、呼吸しづらさ、咳、喘鳴といった症状が引き起こされます。
適切な治療を行えば、症状を抑えながら日常生活を送ることが可能です。一方で、適切な治療を行わないでいると、発作的な症状が繰り返されるだけでなく、命にかかわる大きな発作へと至ることがあります。
日本人の気管支喘息有病率は約8%にも及ぶとされ、身近な病気ではありますが、そのうち受診し治療を受けている人は1割程度と言われています。健康・命、そしてQOLを守るため、症状がある方は放置せずお早目にご相談ください。
気管支喘息の症状チェック
気管支喘息には、さまざまな症状が見られます。
一般的な症状と、自覚しにくい症状(気管支喘息の症状だと気づきにくい症状)に分けてご紹介します。
一般的な症状
- 呼吸のしづらさ
- 咳、痰
- ゼーゼー、ヒューヒューという呼吸(喘鳴)
- 息切れ
- 胸の圧迫感
- のどが詰まる感じ
- のどのイガイガ感
- 深呼吸ができない
自覚しにくい症状
- 冷気、砂埃、煙、香水などにより誘発される咳
- 運動、疲労、ストレス、睡眠不足などにより誘発される咳
- 入浴時に出る咳
- 夜間~早朝にかけての咳
- 風邪のひきやすさ
気管支喘息の原因
 気管支喘息は、アレルギーによる「アトピー型」と、アレルギーが関与しない「非アトピー型」に分けられます。
気管支喘息は、アレルギーによる「アトピー型」と、アレルギーが関与しない「非アトピー型」に分けられます。
大人の場合は非アトピー型が、子どもの場合はアトピー型が多くなります。
アレルギー
特定の食物、ハウスダストなどがアレルゲンとなり、症状が引き起こされます。
感染症
風邪やインフルエンザにかかった時には、気道の炎症が強くなり、気管支喘息の症状が強く現れます。
自律神経の乱れ
ストレス、睡眠不足、不規則な生活リズムなどを原因として自律神経が乱れると、気道が収縮しやすくなることから、気管支喘息の原因となることがあります。また、抵抗力も低下し、風邪などにかかりやすくなります。
環境因子
PM2.5や黄砂など有害物質の吸入、気温の変化、空気の乾燥なども、気管支喘息の原因となります。
運動
運動に伴う換気量の増大によって気管支が刺激され、炎症が起こったり、収縮が誘発されることがあります。
気管支喘息の検査・診断
気管支喘息は、慢性的な気道の炎症を伴う病気です。
適切な治療によって症状をコントロールするためには、正確な検査・診断が重要となります。
問診
問診では、以下のようなことをお尋ねします。
- 症状の種類
- いつから症状が続いているか
- 発作の出る時間帯やタイミング(夜間・早朝・外出時・運動時など)
- ハウスダスト、特定の食物など、関連の疑われる因子について思い当たること
- 気管支喘息の家族、アレルギー体質の家族がいるかどうか
- 既往歴、服用中の薬
原因の絞り込み、検査の選択、正確な診断のため、問診の内容は非常に重要です。
身体診察:呼吸音や胸の動きをチェック
聴診器を胸に当て、呼吸音、喘鳴の有無などを調べます。ただし、診察時に症状が出ていないこともあります。
呼吸機能検査(スパイロメトリー)
 肺活量、息を吐くスピードを調べたり、その2項目の対比から、気道の狭窄の程度を判定します。
肺活量、息を吐くスピードを調べたり、その2項目の対比から、気道の狭窄の程度を判定します。
また、気管支拡張薬を使用し、改善するかどうかを調べることが、気管支喘息との関連の確認にも役立ちます。
呼気中一酸化窒素(FeNO)検査
吐いた息(呼気)に含まれる一酸化窒素の濃度を測定し、気道の炎症の程度を調べます。特にアトピー型の気管支喘息の場合、この値が高くなります。機械に向かって息を吐くだけの、簡単な検査です。
血液検査・アレルギー検査
血中の好酸球の数、IgEの値を測定し、アレルギーの関与について調べます。また必要に応じて、アレルゲンを特定する検査も実施します。
胸部レントゲン検査
気管支喘息と似た症状を持つ肺炎、肺がん、COPD(慢性閉塞性肺疾患)を除外するため、レントゲン検査を行います。
気管支喘息は、症状が出たり落ち着いたりを繰り返すために、「治ったかな?」「また出たけど、すぐ治まるだろう」と、受診のタイミングを逃しがちです。
症状が落ち着いた状態であっても、上記のような問診・検査を行うことで、診断が可能です。
早期に適切な治療を行うため、どうぞお早目に当院にご相談ください。
気管支喘息の治療
気管支喘息に対しては、発作時の治療と、非発作時の治療が必要になります。
発作時の治療法
咳、喘鳴、呼吸困難などの急性症状が現れた時に行う治療です。
主な薬剤
- 短時間作⽤性吸⼊β2刺激薬…短時間で気管支を広げ、症状を和らげます。
- 経口ステロイド薬…重い症状が現れている場合に使用します。短時間で気道のむくみを改善し、症状を和らげます。
長期使用によって骨密度低下・血糖値上昇・感染・血栓症のリスクが高くなるため、短期間のみ使用します。
非発作時の治療法(予防的治療)
発作を予防するために、普段から行う治療です。
主な薬剤
- 吸入ステロイド薬…気管支の炎症を和らげます。
- 長時間作用型抗コリン薬…長時間にわたって気管支を拡げ、症状を和らげます。
- 長時間作用性β2刺激薬…長時間にわたって気管支を広げます。
- 長時間作用型β2刺激薬配合剤…2種類の薬剤成分により、長時間にわたって気管支を広げます。
- ロイコトリエン受容体拮抗薬…気道の炎症を和らげます。・テオフィリン徐放薬…気道の炎症を和らげます。
気管支喘息の患者さんが気を付けるべき日常生活の注意点
気管支喘息は、お薬を使った治療に加え、日常生活において以下のような点に気をつけることで、より症状が落ち着きやすくなります。
身発作を誘発するトリガーを避ける
小まめな掃除・寝具の清潔維持などによるハウスダスト対策、マスク着用や外出機会の選択によるPM2.5・黄砂・花粉対策、マスク・マフラーなどによる冷気・温度変化対策、ストレス解消・十分な睡眠・規則正しい生活による自律神経の乱れへの対策などがあります。
また喫煙をしている人は禁煙し、受動喫煙もしないようにしてください。
症状が落ち着いても薬物療法を継続する
気管支喘息は、症状が出たり落ち着いたりを繰り返します。症状が落ち着いた時、自己判断で薬物治療をやめてしまうと、高確率で再燃します。
症状が落ち着いても、定期的な通院、そして適切な治療を継続しましょう。
感染症の予防に努める
風邪、インフルエンザなどの感染症は、症状を悪化させる原因となります。
手洗い・うがい、人混みを避ける、外出時のマスク着用などで、感染症の予防に努めましょう。インフルエンザワクチン、肺炎球菌ワクチンなどの予防接種も有効です。
軽い運動の継続により気道を鍛える
呼吸が激しく乱れるような運動は、発作を誘発する因子です。一方で、ウォーキング、ストレッチ、ヨガなどの軽い運動には、気道を鍛え、発作が起こりにくくなる効果が期待できます。年齢、体力に合わせた運動を継続しましょう。
規則正しい生活により免疫力を維持する
バランスの良い食事、適度な運動、ストレス解消、十分な睡眠などによって体調を整えましょう。感染症の予防という意味でも有効です。
薬物療法に加え、生活習慣の改善に取り組むことで、より治療の効果は高まります。
無理のない範囲で、生活を改善していきましょう。