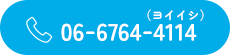循環器内科について
 循環器内科は、血管や心臓などの全身の血液循環に関わる臓器を専門とする診療科です。診察するのは、心筋梗塞のような命に関わる疾患だけではありません。高血圧、脂質異常症、動脈硬化、動脈瘤、不整脈、狭心症・心筋梗塞といった虚血性心疾患、弁膜症、心筋疾患、心不全など、循環器系全般の疾患に対応しています。
循環器内科は、血管や心臓などの全身の血液循環に関わる臓器を専門とする診療科です。診察するのは、心筋梗塞のような命に関わる疾患だけではありません。高血圧、脂質異常症、動脈硬化、動脈瘤、不整脈、狭心症・心筋梗塞といった虚血性心疾患、弁膜症、心筋疾患、心不全など、循環器系全般の疾患に対応しています。
専門的な治療はもちろん、早期発見のための検査、進行の予防なども循環器内科の役割です。健康診断で心電図異常を指摘されたり、動悸や息切れがするといった症状でお困りの際は、大阪市にある鶴橋駅前よしかわ内科の循環器内科へご相談ください。
循環器内科で相談される症状
 循環器内科では、主に以下のような症状に対応しています。
循環器内科では、主に以下のような症状に対応しています。
心当たりがある方は、一度ご相談ください。
- 脈が飛ぶ
- 脈が遅くなる(徐脈)
- 脈が速くなる(頻脈)
- 胸が苦しい
- 胸の真ん中・左・右が痛い(ズキズキ)
- 背中や左腕から肩にかけて痛い
- 動悸が止まらない・息苦しい
- 息切れ(呼吸困難)
- 手・足・顔のむくみ(何科?)
- 失神(意識消失)病院に行くべきか(何科?)
- 冷え性(足先)
- 足先が痛い
- など
循環器内科で診療する疾患
心不全
心不全は、様々な原因で心臓のポンプ機能が弱まって体中に十分な血液を送れなくなった状態を指します。心筋梗塞や弁膜症、心筋症、長年の高血圧など、多くの心疾患が心不全の原因になる可能性があります。
典型的な症状は、息切れや足のむくみです。初期には階段の上り下りや坂道を登る時に息切れを感じる程度ですが、進行するとわずかな歩行でも息苦しくなります。さらに進行すると、安静時でも息苦しさを感じ、横になると呼吸が苦しくなるため眠ることさえ困難になることがあります。
特にご高齢の方は、このような症状を「歳のせい」と考えて受診が遅れがちなため注意しましょう。
心筋症
心筋症とは、心筋(心臓の筋肉)の異常によって、心臓の機能が低下していく病気です。心臓の収縮性が低下して拡張する「拡張型」、心臓が肥大する「肥大型」、心臓の拡張が高度に障害される「拘束型」に分けられます。遺伝子異常、ウイルス感染などの原因が挙げられますが、原因が特定できないケースも少なくありません。そのため、厚労省より難病の指定を受けています。
主な症状
初期には無症状であることが多いものの、進行すると息切れ、動悸、むくみ、夜間の咳・息苦しさなどの症状が現れます。さらに進行すると、食欲不振、歩行困難など、重大な症状も出現します。
診断・治療法
血液検査、レントゲン検査、心電図検査、心臓エコー検査、心臓CT検査、心臓MRI検査、心筋シンチグラフィ、心臓カテーテル検査などを行い、診断します。
治療では、ベータ遮断薬やACE阻害薬、アンギオテンシン受容体拮抗薬などを用いた薬物療法が中心となります。
狭心症
狭心症には、主に2つのタイプがあります。運動時などに胸部痛が生じる「労作性狭心症」と、安静にしている夜間や早朝に胸痛を感じる「冠攣縮性狭心症」です。
労作性狭心症は、心筋に血液を供給する冠動脈が動脈硬化によって狭くなることで発症します。診断には心臓CT(冠動脈CT)や心臓カテーテル検査(冠動脈造影)を用いて、血管がどれくらい狭窄しているか評価します。治療は薬物療法が基本ですが、症状や狭窄の程度によっては、カテーテルを使用した血管拡張術や冠動脈バイパス手術などの外科的処置も検討されます。
一方、冠攣縮性狭心症(異型狭心症)は、特に就寝中の夜間や早朝に胸痛が発生すると言われ、冠動脈が一時的にけいれんを起こすことで血流が妨げられて発症します。この場合、心臓CTなどで冠動脈に物理的な狭窄がないことを確認した上で、ニトログリセリンといった血管拡張薬を発作時に投与し、その効果を見ることで診断と治療を同時に進めることが多いです。
診断が難しい場合や薬の効果が十分でない患者さんには、心臓カテーテル中に意図的に冠動脈のけいれんを誘発する検査を行うこともあります。また、喫煙や特定の化学物質への暴露が発作の引き金になることも多いため、生活習慣の改善も重要な治療です。
心筋梗塞
心筋梗塞は、心臓を動かす筋肉(心筋)に血液を運ぶ血管(冠動脈)が詰まってしまい、酸素や栄養が心筋に届かずに壊死してしまう疾患です。発症すると、強い胸の痛みや締め付けられるような圧迫感が現れます。同時に冷や汗が出たり、吐き気を感じたりすることも多いです。この状態が続くと命に関わる危険な状態になります。
心筋梗塞は、主に血管の内側にコレステロールなどが溜まる「動脈硬化」が原因で起こります。高血圧、糖尿病、喫煙、脂質異常症(高脂血症)などは動脈硬化を進めてしまう要因です。何の前触れもなく突然発症しますが、運動した時など一時的に胸が痛くなる「狭心症」の症状が悪化して心筋梗塞になることもあります。
心筋梗塞と診断されたら、ほとんどの場合で早急なカテーテル治療が必要になります。もし胸の痛みが続くようであれば、様子を見ずにすぐに救急車を呼ぶようにしましょう。
不整脈
心拍が通常とは違うパターンで発生し、心臓の鼓動が一定ではない状態を不整脈と言います。不整脈は、心拍が通常とは違うパターンで発生し、心臓の鼓動が一定でなくなる状態を指します。不整脈には大きく分けて
- 心拍が遅くなる「徐脈」
- 心拍が速くなる「頻脈」
- 心拍が抜ける「期外収縮」
の3タイプが存在します。
軽度の不整脈であれば、特に治療しなくても問題ない場合があります。一方、生命に危険を及ぼす重篤な不整脈もあり、迅速な処置が必要です。
主な原因として、心臓弁膜症や虚血性心疾患、先天的な心臓の異常、心機能低下などのほか、遺伝的素因による不整脈や、肺疾患、甲状腺疾患、強いストレス、睡眠不足、過度の疲労などがあります。
心臓弁膜症
心臓弁膜症は、様々な原因で心臓の弁が正常に機能しなくなる病気です。心不全の原因の1つでもあるため注意が必要です。進行すると心臓の働きが低下して、症状が現れます。
主な症状は、息切れが最も多く、特に歩行時や坂道を登る時に強く感じることがあります。そのほか、疲れやすさ・失神・胸痛・めまいなどの様々な症状が現れることがあります。
治療には、薬による内科的治療だけでなく外科手術が必要になる場合もあります。近年ではカテーテルを用いた治療が導入され、ご高齢の方でも治療が受けられるようになっています。
肺高血圧症
肺高血圧症は、肺動脈の血圧が高くなる疾患の総称です。肺動脈の血圧が高くなると、壁が肥厚して血管内圧が増加し、心臓にかかる負担が大きくなります。その結果、息切れや脚のむくみ、全身の倦怠感などの症状が現れる可能性があります。
最も特徴的な症状は息切れですが、肺高血圧以外の疾患でも現れるため、発見されずに診断が遅くなる可能性があります。また、受診しても診断に結びつかない可能性もあります。この疾患は診断や治療の遅れその後の経過に悪影響を及ぼすため、早期発見と適切な治療が重要な疾患です。
心肥大
心肥大とは、心筋が厚くなることを指します。心臓の機能が低下し、全身に十分な血液を送り届けることができなくなります。不整脈のリスクが高くなり、突然死の原因になることもあります。
主に高血圧を原因として発症します。また、心臓弁膜症、心筋梗塞に合併しやすい病気であり、進行すると心不全の状態になります。
主な症状
疲れやすさ、動悸、息切れ、呼吸困難、むくみ、胸痛、食欲不振、倦怠感などの症状を伴います。
診断・治療法
胸部レントゲン検査、心電図検査、心臓エコー検査などを行い、診断します。エコー検査では、心筋の厚み、心肥大の原因などを調べることができます。
治療では、主な原因となる高血圧に対する治療が中心となります。血圧を下げるお薬の内服、生活習慣指導を行います。
動脈硬化
動脈硬化は、名前の通り動脈の壁が硬くなった状態です。加齢によって自然に進行する面もありますが、特に血中のコレステロール値が大きく関与します。一般に「悪玉コレステロール」と呼ばれるLDLコレステロールが多く、「善玉コレステロール」と呼ばれるHDLコレステロールが少ない状態では動脈硬化が進行しやすいとわかっています。
動脈硬化が進行すると、心血管に負担がかかって心機能が低下することがあります。また、硬くなった血管は破裂しやすくなり、命に関わる疾患の発症リスクが高まります。
慢性腎臓病(CDK)
慢性腎臓病とは、腎機能の低下が認められる、または腎臓に障害がある病気のことを指します。長期にわたって放置していると、人工透析が必要になります。一方でなかなか自覚症状が現れにくいことから、腎機能の検査で異常を指摘された場合には、症状の有無に関係なく治療を行うことが大切です。早期であれば腎機能の改善が見込めますが、進行した場合には改善が期待できません。
主な症状
先述の通り、初期にはほとんど自覚症状がありません。進行すると、夜間の尿量の増加、貧血、立ちくらみ、手足のむくみ、疲労感、息切れ、不整脈、頭痛、視力低下、意識障害などの症状が現れます。そしてこれらの症状が現れるのは、人工透析が必要になる直前というのが、慢性腎臓病のおそろしさと言えます。
診断・治療法
血清クレアチニン・eGFRを調べる腎機能検査、尿蛋白を調べる尿検査、電解質・貧血などを調べる血液検査等を行い、診断します。
治療では、食事療法を中心とした生活習慣の改善、降圧剤・腎保護薬などを用いた薬物療法を行います。
高血圧症
高血圧症とは、複数回測定しても血圧が基準値を上回っている状態が続く疾患です。診断基準は合併症の有無や年齢によっても異なりますが、一般的には診察室で測った血圧が140mmHg以上または拡張期血圧が90mmHg以上、家庭で測定した血圧が135mmHg以上または拡張期血圧が85mmHg以上の場合は高血圧と診断されます。
高血圧症は大きく「本態性高血圧」と「二次性高血圧」に分類され、一般的に高血圧と呼ばれるのは本態性高血圧です。過剰な塩分摂取、体重過多、精神的ストレスなど生活習慣が主な原因となります。
「二次性高血圧」には腎機能異常やホルモンバランスの乱れなどの原因となる疾患が存在します。そのほか、薬剤性高血圧や、睡眠時無呼吸症候群などで生じる場合もあります。
高血圧を発症しても自覚症状が乏しく、放置すると動脈硬化が促進されて心疾患や脳血管障害の発症リスクが高くなります。早期発見と適切な管理・治療が不可欠です。
動脈瘤
動脈瘤とは、動脈の壁の一部が薄くなり、血管がこぶのように膨らむ病気です。膨らんだ部分の壁は脆く、圧力がかかると破裂して、場合によっては命に関わることもあります。
主な原因としては高血圧・喫煙・加齢などが挙げられます。動脈瘤は破裂するまで自覚症状がないことが多いですが、まれに神経の圧迫による声のかすれや、お腹の拍動に気づくことで受診し、発見される場合もあります。
動脈瘤が大きくなると破裂のリスクが高まり、突然の激しい胸や腹の痛みが生じることがあります。動脈瘤破裂の死亡率は90%という報告もあるため、緊急手術が必要な状態です。
閉塞性動脈硬化症
足の血管の動脈硬化が進行し、血流が低下することで発症する疾患です。初期症状として足の痛みやしびれが見られますが、進行すると安静時にも痛みを感じるようになり、さらに切り傷などが治らず壊死してしまうこともあります。
主に50~60歳以降の中高年の方に多く見られますが、特に高血圧・糖尿病・慢性腎臓病・喫煙など、動脈硬化のリスク因子を持つ人に発症しやすいとされています。また、この病気を持つ人は狭心症や脳梗塞などほかの動脈硬化性疾患を合併していることも多いため、注意が必要です。
深部静脈血栓症・肺閉塞症
深部静脈血栓症とは、足の静脈に血栓が生じて血管が塞がったために炎症が起こり、腫れや痛みを伴う病気です。エコノミークラス症候群とも呼ばれています。できた血栓が剥がれて血流に乗って移動し、肺の血管に詰まると「肺塞栓症」と診断され、重篤な状態に陥ることもあります。
深部静脈血栓症の主な症状は、片方の足の腫れやむくみ、ふくらはぎを押すと感じる痛みなどです。もし肺血栓塞栓症を発症すると、息苦しさや動いた際の息切れといった症状が現れることがあります。
循環器内科で実施可能な検査
血液検査
糖尿病や脂質異常症など、循環器疾患のリスクを高める病気の有無や、必要に応じて心臓への負担を数値化して心不
全の重症度を評価するBNPまたはNT-proBNP、心筋梗塞などの診断に役立つ心筋トロポニンなどを調べます。
心電図検査
身体に電極を付け、心臓の電気的な活動を測定する検査です。動悸や脈の異常、胸の痛みがある場合などに、狭心症・心筋梗塞・不整脈の可能性を調べるために行われます。
胸部レントゲン検査
心臓・肺・大動脈の状態を確認するための検査です。心臓が大きくなる心拡大、肺の血管の血液増加によって起こる肺うっ血、胸に液体が溜まる胸水の有無を調べます。これらの異常は心不全の患者さんに起こりやすいと言われています。
超音波検査(心エコー検査)
胸にゼリーをつけたプローブを当て、超音波を用いて心臓や血管を映し出して検査します。非侵襲性で痛みはありません。心臓の形・大きさ・動き・血流の状態の評価や、心臓弁膜症・先天性心疾患・心嚢水の有無の確認のために行われます。
ホルター心電図
小型の機械を装着し、長時間(24時間)にわたって心電図を記録する検査です。日常生活の中での不整脈(期外収縮・心房細動・心室頻拍など)を診断するのに役立ちます。心電図解析の際の参考情報として、検査中に動悸や胸痛が出た際にはボタンを押して記録していただきます。
装置は院内で装着して1日過ごし、翌日に返却となります。
血圧脈波検査(動脈硬化検査、血管年齢検査)
動脈硬化の進行度や血管の老化を評価する検査です。両手・両足の血圧と脈波を測定して、閉塞性動脈硬化症の診断などにも活用される検査です。測定時に血圧のカフが締まりますが、基本的に痛みがない非侵襲性の検査です。
頸動脈エコー
左右の首元から脳にかけて存在する太い血管「頸動脈」の状態を、超音波を用いて調べる検査です。動脈硬化による血管壁の肥厚やプラークの有無を評価したり、狭窄の程度を把握し、脳梗塞・心筋梗塞のリスクを推測したりできます。高度な狭窄がある場合、カテーテル治療が必要になることもあります。
冠動脈造影検査
手首や足の血管からカテーテルを挿入し、心臓の血管(冠動脈)の狭窄や閉塞の有無を調べる検査です。造影剤を用いたX線撮影により、冠動脈の狭窄度を評価します。
最近はFFR(冠血流予備量比)という検査を併用し、狭窄部位で血流量がどれくらい低下しているか評価することが多くなっています。検査の際は、原則として入院が必要です。
この検査が必要と判断された場合は、当院より提携している医療機関をご紹介します。