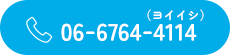冷え性(足先)でお困りの方へ
 冬の外出時はもちろん、夏でもエアコンの効いた環境では冷えを感じることがあります。通常は衣服の調整などで対応できますが、「冷え性」の場合はそう簡単ではありません。周囲の人が心地良いと感じる温度でも、手足が冷たく感じたり、内側から冷えを感じたりします。
冬の外出時はもちろん、夏でもエアコンの効いた環境では冷えを感じることがあります。通常は衣服の調整などで対応できますが、「冷え性」の場合はそう簡単ではありません。周囲の人が心地良いと感じる温度でも、手足が冷たく感じたり、内側から冷えを感じたりします。
冷え性の方は、特に足の冷えでお悩みかと思います。「厚い靴下を履いても」「暖かい布団に入っても足が冷たい」という状態は、単なる寒さではなく冷え性の可能性があります。足先の冷えは不快感だけでなく、睡眠の質や全身の健康状態にも影響を及ぼし、生活の質を低下させます。
冷え性でお悩みの方は、生活習慣の見直しや適切なケアで症状が改善することも多いです。気になる症状がある方は、大阪市の鶴橋駅前よしかわ内科へお気軽にご相談ください。
足先の冷え症状が
引き起こす問題
足先の冷えは「ただ冷たいだけ」と軽視されがちですが、実は全身の健康に影響を及ぼす可能性があります。
睡眠の質の低下
私たちが眠りにつく際は、手足から熱を放出して体の中心部の温度を下げることで、休息モードに入ります。しかし、冷え性の方は日中から体温が上がりにくく、夜になっても体が防御反応として熱を過度に放出しないようにするため、自然な体温調節がうまくいきません。その結果として寝つきが悪くなり、睡眠の質が低下します。
全身の冷えと免疫力低下
足先の冷えは徐々に全身の冷えに発展し、様々な体調不良を引き起こす可能性があります。特に腹部が冷えると腸の働きが低下し、消化不良や便秘の原因になります。また、全身の冷えは免疫力の低下にもつながり、風邪やその他の感染症にかかりやすくなることもあります。
冷え性(足先)の原因や
男女の違い
冷え性には様々な原因があり、生活習慣や体質、時には病気が関係していることもあります。主な原因として以下のようなものが挙げられます。
基礎代謝の低下
基礎代謝とは、生命維持に必要な最低限のエネルギー消費量のことです。加齢、運動不足、筋肉量の減少などにより基礎代謝が低下すると、体温を維持する力が弱まり、冷え性につながります。
年齢を重ねるにつれて基礎代謝は自然に低下するため、中高年になると冷え性になりやすくなります。
栄養バランス・食生活の乱れ
偏った食生活やダイエットによる栄養不足は、筋肉量の減少や血行不良を招き、冷え性の原因となります。特に鉄分やビタミンE、ビタミンB群などのミネラルやビタミンが不足すると、血液循環に悪影響を及ぼします。
また、不規則な食事や過度な食事制限は基礎代謝の低下にもつながります。
慢性的なストレス
ストレスを感じると交感神経が優位になり、血管が収縮して血流が悪くなります。長期的なストレスは自律神経のバランスを崩し、手足の血管の収縮が続くことで冷えを引き起こします。
自律神経の乱れ
ストレス、不規則な生活、睡眠不足などで自律神経のバランスが崩れると、血管の収縮・拡張がうまく調整できなくなります。また、自律神経の乱れは胃腸の働きも低下させ、全身の代謝機能に影響を与えることで冷え性を悪化させます。
喫煙
タバコに含まれるニコチンには血管を収縮させる作用があり、喫煙は血行不良を招きます。そのため、喫煙者は末梢循環が悪化し、冷え性になりやすい傾向があります。
女性特有の冷え性の原因
女性は男性と比べて冷え性に悩む方が多く、その背景には以下のような要因があります。
筋肉量が少なく、脂肪が多い
女性は男性に比べて筋肉量が20~30%ほど少なく、体脂肪率が高い傾向にあります。筋肉は熱を生み出す器官なので、筋肉量が少ないと熱生産が少なくなります。また、脂肪は一度冷えると温まりにくい性質があるため、冷え性になりやすいと言えます。
骨盤内の血流低下
女性は子宮や卵巣など骨盤内の臓器があるため、男性に比べて腹部の血流が低下しやすい傾向があります。これにより下半身の冷えを感じやすく、体の末端にある手足が特に影響を受けます。また、月経周期によるホルモンバランスの変化も血流に影響します。
足を出す服装、露出の多い服装が多い
スカートやドレスなど脚を露出する機会が多い服装や、タイトな衣類、締め付けのあるベルトなどは血流を妨げ、下半身の冷えを助長します。
男性特有の冷え性の原因
男性の冷え性の主な原因は、加齢や運動不足による筋肉量・基礎代謝の低下、デスクワークなどによる長時間の同じ姿勢、食生活の乱れ、ストレス、喫煙などです。特に男性の場合、肩こりや腰痛といった筋肉の緊張から血行不良になり、冷え性を自覚するケースが多いようです。
男性の冷え性は女性ほど一般的ではありませんが、近年増加傾向にあります。
冷え性は病気が
関係しているかも?!
下肢閉塞性動脈硬化症・
下肢末梢動脈閉塞症
下肢閉塞性動脈硬化症(ASO)
動脈硬化によって足の動脈が狭くなり、血流が低下する病気です。最初は足先の冷えやしびれとして現れますが、進行すると歩行時の足の痛み(間欠性跛行)が現れます。
さらに重症化すると安静時でも痛みが続き、皮膚の色が変わったり潰瘍ができたりすることもあります。喫煙者、高血圧や糖尿病の方、高齢者に多く見られます。
下肢末梢動脈閉塞症(PAD)
足への血流が不足する病気で、動脈の狭窄や閉塞によって引き起こされます。足先の冷えのほか、歩行時の足の痛み(間欠性跛行)も現れます。進行すると足の皮膚の乾燥や傷の治りにくさなどの症状も引き起こします。
様々な生活習慣(喫煙、糖尿病、高血圧など)がリスク要因となるため、早期受診と生活習慣の見直しが大切です。
動脈硬化
血管の壁が厚く硬くなり、血流が悪くなった状態です。加齢、高血圧、脂質異常症、喫煙などが原因となります。足の血管が影響を受けると、血流不足で足先が冷えやすくなります。
動脈硬化は心臓病や脳梗塞のリスクも高めるため、食生活の改善や適度な運動を心がけましょう。
バージャー病
四肢の動脈に炎症が起こり、血管が詰まって末端部分が壊死することもある深刻な病気です。未だ原因ははっきりとしていませんが、若い男性(10〜20代)に多く、喫煙や歯周病との関連が指摘されています。
足指の冷え、しびれ、蒼白、歩行時の痛み、安静時の痛みなどの症状が現れ、進行すると潰瘍や壊死に至ることもあります。早期発見と禁煙が何よりも重要です。
レイノー病
寒さやストレスなどによって動脈が過剰に収縮した際に、指先が白色あるいは紫色に変色する病気です。原因不明の一次性レイノー病と、リウマチや強皮症などの膠原病に伴う二次性レイノー病があります。症状がある場合は、適切な診断と治療が必要です。
冷え性(足先)の対策・治し方(入浴・運動・食事など )
冷え性は日常生活の工夫で改善できることも多いです。以下のような方法を生活に取り入れてみましょう。
入浴について
 シャワーだけでなく、湯船にしっかりつかることが冷え性改善の基本です。38〜40℃程度のぬるめのお湯に、じんわりと汗をかく程度まで浸かりましょう。熱すぎるお湯で体が温まっても、その後急激に熱が逃げてしまうため逆効果です。
シャワーだけでなく、湯船にしっかりつかることが冷え性改善の基本です。38〜40℃程度のぬるめのお湯に、じんわりと汗をかく程度まで浸かりましょう。熱すぎるお湯で体が温まっても、その後急激に熱が逃げてしまうため逆効果です。
入浴中にゆっくり深呼吸すると、副交感神経が優位になり、血管が拡張して血行が良くなります。また、入浴前後に水分補給をすることで、血液の循環も良くなります。
運動について
血行を良くするためには、適度な運動で新陳代謝を促進することが効果的です。激しいスポーツである必要はなく、日常生活の中で少し多めに歩いたり、階段を使ったり、ストレッチを取り入れたりするだけでも効果があります。
特に就寝前の軽いストレッチは、血行を促進して体温を上げ、質の良い睡眠につながります。日々の生活の中で体を動かす習慣をつけていきましょう。
食事について
 冷たい食べ物や飲み物の摂り過ぎは体を冷やす原因になります。特に夏場はつい冷たいものを選びがちですが、常温の飲み物を意識的に選ぶようにしましょう。また、睡眠中は気づかないうちに脱水状態になりやすいです。就寝前と起床後に水分補給をすることで、血液循環を維持し、脱水を予防できます。
冷たい食べ物や飲み物の摂り過ぎは体を冷やす原因になります。特に夏場はつい冷たいものを選びがちですが、常温の飲み物を意識的に選ぶようにしましょう。また、睡眠中は気づかないうちに脱水状態になりやすいです。就寝前と起床後に水分補給をすることで、血液循環を維持し、脱水を予防できます。
飲み物について
体を温める効果がある飲み物
紅茶、ほうじ茶、烏龍茶、ココア、生姜湯
摂りすぎると体を冷やす可能性がある飲み物
コーヒー(カフェイン)、緑茶(カフェイン)、冷たいジュース、冷たい水、冷たい牛乳
呼吸について
腹式呼吸(息を吸う時にお腹が膨らみ、吐く時にへこむ呼吸法)は、副交感神経を活性化してリラックス効果をもたらしてくれます。腹式呼吸によって自律神経のバランスが整い、血行改善が期待できますので、日常生活の中で1日5分程度でも意識して行いましょう。
朝起きた時、仕事の合間、入浴中、寝る前などが実践しやすいのでおすすめです。
マッサージについて
 マッサージは血行を促進する手軽な方法です。特に入浴後は血行が良くなっているため、クリームやオイルを使って足をマッサージすると効果的です。
マッサージは血行を促進する手軽な方法です。特に入浴後は血行が良くなっているため、クリームやオイルを使って足をマッサージすると効果的です。
毎日5〜10分程度、足の指先から太ももに向かって優しくマッサージするだけでも、血行が改善されます。冷たく感じる部分を重点的にケアし、強く刺激しすぎないよう注意しましょう。