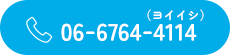長引く咳
(2週間以上続いている)方へ
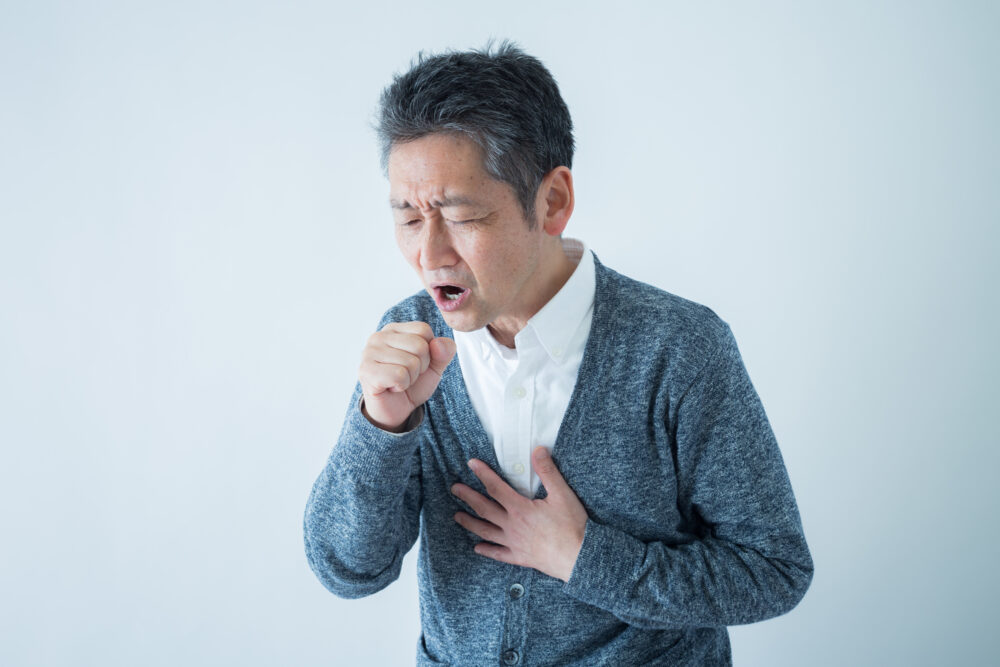 風邪に伴う咳は多くの場合、1週間以内に落ち着きます。それ以上の期間、咳が続く場合には、風邪ではない病気が原因になっている、風邪をきっかけに合併症が引き起こされているといったことを疑う必要があります。
風邪に伴う咳は多くの場合、1週間以内に落ち着きます。それ以上の期間、咳が続く場合には、風邪ではない病気が原因になっている、風邪をきっかけに合併症が引き起こされているといったことを疑う必要があります。
特に2週間以上続く咳は、医学的にも「長引く咳」と捉え、診察、詳しい検査を受けることが大切になります。
「そのうち治るだろう」と放置せず、お早目に当院にご相談ください。もちろん、2週間に満たなくても、気になる場合には受診をおすすめします。
咳が長引くときに考えられる病気
咳が長引く時には、循環器疾患や呼吸器疾患を疑います。
また、薬の副作用が原因となっているケースもあるため、受診の際にはお薬手帳をお持ちください。
循環器疾患が原因となる場合
血液が循環する器官、つまり心臓や血管の病気を原因として、咳、息切れなどの症状が慢性化することがあります。
心臓弁膜症
心臓の弁に異常が生じ、血液が逆流すると、肺が圧迫されます。これにより、咳や息苦しさが慢性化します。
高血圧性心疾患
長年にわたる高血圧の影響で心臓に負担がかかると、心拡大・心不全をきたし、咳が続くことがあります。
肺高血圧症
肺動脈の血圧が高くなると、咳・呼吸困難などの症状が引き起こされます。進行性の病気であり、症状も次第に悪化します。
降圧薬(ACE阻害薬)による副作用
降圧薬として使用されるACE阻害薬は、副作用として乾いた咳が見られることがあります。必要に応じて、お薬を変更します。
呼吸器疾患が原因となる場合
咳が長引く場合、まず疑うのは呼吸器疾患です。咳に加えて、喘鳴、痰などの症状を伴うことが多くなります。
急性気管支炎・
ウイルス性上気道炎
風邪をひいても、咳などの症状の多くは1週間以内に治まりますが、2週間以上続くということもあります。
咳喘息
喘息のうち、喘鳴を伴わず、咳のみが続くタイプです。特に夜間、明け方に強い咳が見られます。
気管支喘息・COPD
(慢性閉塞性肺疾患)
どちらも、慢性の咳・痰・呼吸困難といった症状が見られます。COPDの主な原因は喫煙です。
肺がん・肺結核
咳に加え、血痰が続く場合には、肺がん・肺結核といった深刻な病気も疑う必要があります。
その他の原因
数は少ないものの、以下のような原因によって咳が長引くことがあります。
胃食道逆流症(GERD)
胃酸が逆流し、気道が刺激されることで、のどの違和感、乾いた咳などが見られます。特に、食後、横になった時、咳が強くなります。
ストレスやアレルギー反応
強いストレス、アレルギーによって咳が引き起こされるというケースも見られます。
長引く咳のときの検査・診断
長引く咳の原因を調べるため、以下のような検査を行います。
胸部レントゲン検査
 肺炎、肺気腫、肺結核、肺がん、心不全などの病気の有無を調べます。
肺炎、肺気腫、肺結核、肺がん、心不全などの病気の有無を調べます。
スパイロメトリー検査
肺活量、息を吐く速さの測定を行い、肺の機能を評価します。
主に、気管支喘息、肺気腫、間質性肺炎などが疑われる場合に実施します。
その他
その他、必要に応じて血液検査、喀痰検査、モストグラフ検査、呼気NO検査、心臓超音波検査、胸部CT検査などを行うこともあります。
長引く咳の治療法
咳止めなどで症状を抑えることは可能ですが、根本的な治療のためには、その原因となっている疾患に応じた治療を行う必要があります。
循環器疾患が原因の場合
 心不全、心臓弁膜症、狭心症などの治療では、心臓の負担を軽減し、血液循環を改善する治療を行います。
心不全、心臓弁膜症、狭心症などの治療では、心臓の負担を軽減し、血液循環を改善する治療を行います。
薬物療法としては、肺うっ血を軽減するための利尿薬、血圧をコントロールし心臓の負担を軽減する降圧薬などが用いられます。
薬物療法で十分な効果が得られない場合には、手術、カテーテル治療などを行います。
呼吸器疾患が原因の場合
気管支炎、喘息・咳喘息、COPDなどに伴う咳は、気道の炎症・過敏性を抑える治療を行います。
気道を広げる気管支拡張薬、炎症を抑える吸入ステロイド薬などを使用します。必要に応じて、生活指導、禁煙サポートなども行います。
市販薬を使い続けるのではなく、医療機関で原因を特定し、専門的な治療を受けましょう。
その他
胃食道逆流症に対しては、胃酸の分泌を抑制する薬を中心とした薬物療法、胃酸の逆流を防ぐための生活習慣指導を行います。
ACE阻害薬の内服が原因となっている場合には、ARBなどの別の降圧薬への変更を行います。
長引く咳の時、
自力でできる対処法
医療機関を受診するまでのあいだは、以下のような対処法によって、咳の軽減に努めましょう。
部屋の加湿・小まめな水分補給
空気の乾燥は、気道への刺激となります。加湿器を用いた部屋の加湿、小まめな水分補給などで対応しましょう。
マスクをしたり、のど飴を舐めたりといった方法も有効です。
刺激を避ける
飲酒、喫煙、香水などは、気道を刺激し咳を誘発します。洗剤の香料が原因となることもあります。できる限り、避けましょう。
安静
心臓への負担を軽減するため、激しい運動、負担の大きい仕事などは避け、できるだけ安静にしておきましょう。夜間は、十分な睡眠をとってください。
頭の位置を高くして眠る
枕、寝具を調整して頭の位置を高くして眠ると、横隔膜が下がり、気道が確保しやすくなります。
これらは、あくまで対症療法の一環であり、病気の根本的な治療にはなりません。
時間を見つけ、できるだけ早く医療機関を受診しましょう。