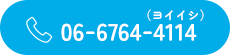むくみ・息切れに要注意!
心不全の初期症状とは?
心不全とは心臓のポンプ機能が低下することで、身体が必要とする血液を十分に送り出せなくなる状態です。軽い症状から始まりますが、進行するとうっ血や呼吸困難などが生じて日常生活に大きな支障をきたします。

急性右心不全の症状
- 肝臓の腫大と右上腹部の痛み(重症の肝うっ血による症状)
- 下肢のむくみ(特に足首やふくらはぎの浮腫)
- 体重の急激な増加(水分貯留による)
- 食欲不振・吐き気(消化器系のうっ血による)
など
急性左心不全の症状
- 起座呼吸(横になると息苦しく、座っていないと呼吸できない状態)
- 夜間発作性呼吸困難(夜間に突然息苦しくなって目が覚める)
- 労作時の強い息切れ(少し動いただけで息切れする)
- 持続する乾いた咳(特に夜間に悪化)
- 疲労感や倦怠感(全身の血流低下による)
など
放置しないで!この症状が
あれば当院へご相談を
息切れや呼吸困難
通常の活動で息苦しさを感じる、または横になると呼吸が苦しくなる場合は、心臓が十分に血液を送り出せず、肺に水分が溜まっている可能性があります。
足首やふくらはぎのむくみ
心臓のポンプ機能が低下すると、体内の水分が適切に循環せず、特に下肢に溜まりやすくなります。靴がきつくなったり、指で押すとくぼみが残ったりするむくみは要注意です。
急激な体重増加
2-3日で2kg以上の体重増加や1週間で3㎏以上の体重増加がある場合は、体内に水分が溜まっている兆候かもし
れません。これは心臓が弱っている重要なサインです。
夜間に呼吸困難で目が覚める
横になっている時に肺に水分が移動しやすくなり、突然の息苦しさで目が覚めることがあります。これは「夜間発作性呼吸困難」と呼ばれ、心不全の典型的な症状です。時に泡状のピンク色の痰が口から出てくることも特徴的です。
心不全について
心不全は心臓のポンプ機能が低下し、身体に必要な血液を十分に送り出せなくなる状態です。心不全になると心臓が血液を効率よく送り出せないため、臓器への血流が不足します。
同時に、静脈や肺に血液がうっ滞し、むくみや息切れなどの症状を引き起こします。
心不全の原因
心不全の主な原因として、虚血性心疾患や高血圧性心疾患、心臓弁膜症や不整脈、心筋症などが挙げられます。また、これら複数の要因が組み合わさって発症することも少なくありません。
虚血性心疾患
虚血性心疾患は心臓の筋肉に血液を供給する冠動脈が狭くなったり、詰まったりすることで起こります。代表的なものに狭心症や心筋梗塞があります。
冠動脈の血流が減少すると、心筋が十分な酸素や栄養を得られなくなり、心臓のポンプ機能が低下します。
高血圧性心疾患
高血圧が長期間続くと心臓は高い血圧に抗って血液を送り出すため、左心室の筋肉が厚くなります。次第に心筋が硬くなり、拡張しにくくなることで心臓の血液充満が妨げられます。
また、長期間の負荷により心臓が拡大して収縮力が低下することもあります。
心臓弁膜症
心臓弁膜症は、心臓の弁が正常に機能しなくなる病気です。弁の異常により心臓のポンプ効率が低下し、心臓に余分な負担がかかります。
この負担が長期間続くと、心臓の筋肉が肥大したり心臓が拡大したりして、心不全を引き起こすことがあります。
心筋症
心筋症は心臓の筋肉に異常がある病気です。代表的なものに拡張型心筋症や肥大型心筋症、拘束型心筋症があります。これらの変化により心臓のポンプ機能が低下し、心不全を引き起こします。
心不全の検査
心不全の診断において血液検査や画像検査、生理機能検査などを実施します。これらの検査によって心不全の有無だけでなく、重症度や原因も判断できます。
血液検査
 血液検査では、心不全の診断や重症度の評価に役立つ特殊なタンパク質を調べます。特にBNPやNT-proBNPは、心臓に負担がかかると増加するため心不全の診断において重要です。
血液検査では、心不全の診断や重症度の評価に役立つ特殊なタンパク質を調べます。特にBNPやNT-proBNPは、心臓に負担がかかると増加するため心不全の診断において重要です。
胸部レントゲン検査
 胸部レントゲン検査では、心臓の大きさや形、肺の状態を観察できます。心不全では心臓が拡大していることが多く、肺に水分が溜まる所見が認められることがあります。
胸部レントゲン検査では、心臓の大きさや形、肺の状態を観察できます。心不全では心臓が拡大していることが多く、肺に水分が溜まる所見が認められることがあります。
心電図検査
 心電図検査では心不全の原因となる不整脈や虚血性心疾患の所見を確認できます。必要に応じて24時間心電図(ホルター心電図)を用いることで、日常生活中の不整脈の有無も詳しく調べることができます。
心電図検査では心不全の原因となる不整脈や虚血性心疾患の所見を確認できます。必要に応じて24時間心電図(ホルター心電図)を用いることで、日常生活中の不整脈の有無も詳しく調べることができます。
心臓超音波検査
 心臓超音波検査は、心臓の大きさや壁の厚さ、収縮力や弁の状態などを詳しく評価することができます。心不全の原因となる弁膜症や心筋症の診断にも役立ちます。
心臓超音波検査は、心臓の大きさや壁の厚さ、収縮力や弁の状態などを詳しく評価することができます。心不全の原因となる弁膜症や心筋症の診断にも役立ちます。
心臓MRI検査
心臓MRI検査は、磁場を用いて心臓の詳細な画像を撮る検査です。放射線被曝がないことが利点ですが、ペースメーカーなどの金属製医療機器を埋め込んでいる患者さんには実施できない場合があります。
※MRI検査が必要と判断された場合は、当院より提携している医療機関をご紹介します。
心臓カテーテル検査
心臓カテーテル検査はカテーテルを心臓まで進めて、心臓内の圧力などを直接測定する検査です。造影剤を注入して、冠動脈の状態を観察する冠動脈造影を行うこともできます。
侵襲的な検査であるため、他の検査で診断が困難な場合や、特殊な治療が必要と考えられる場合に実施されることが多いです。
心不全の治療
心不全の治療方法は生活習慣の改善を行う非薬物療法や、実際に薬物を使用する薬物療法などがあります。
生活習慣の改善
生活習慣の改善は、心不全の症状のコントロールや進行の抑制に大きく影響します。適切な生活習慣の改善により薬物治療の効果が高まり、重症化のリスクを減らせます。
運動
運動療法では、有酸素運動を中心にご自身の体力に合わせて少しずつ運動量を増やしていくことが大切です。運動前後の準備運動やクーリングダウンも忘れずに行いましょう。
食事
塩分の過剰摂取は水分貯留を引き起こし、むくみや息切れなどの症状を悪化させるため、適切な塩分制限と水分バランスの管理が重要です。
タバコ・飲酒・その他注意点
禁煙
タバコは血管を収縮させ、心拍数を増加させることで心臓に負担をかけます。また、長期的には動脈硬化を促進し心臓病のリスクを高めます。心不全の患者さんは必ず禁煙するようにしましょう。
飲酒
アルコールの過剰摂取は心筋に直接的な障害を与え、不整脈を誘発するなど心不全を悪化させる可能性があるため、医師と相談の上、飲酒量をコントロールしましょう。
感染症の予防
心不全の患者さんは感染症にかかると症状が悪化しやすいため予防が重要です。手洗いやうがいの徹底、人混みを避けることやマスクの着用など、感染予防策を心がけてください。
便秘の予防
便秘は排便時に強くいきむことで血圧が上昇し、心臓に負担をかけるため、便秘にならないように十分な水分摂取や食物繊維の摂取、適度な運動を心がけることが大切です。
入浴
入浴時の熱いお湯は血圧を急激に変動させ心臓に負担をかけるため、ぬるめのお湯に短時間入るようにしましょう。浴
室と脱衣所の温度差をなくすことも大切です。
(入浴中に状態が悪くなることもあるため普段から半身浴を心がけましょう。)
薬物療法
心不全の治療における薬物療法では、症状の緩和や心臓への負担軽減、病気の進行抑制などを目的として様々な種
類の薬を用います。(内服を怠ると数日怠るだけで心不全が悪化し生命にかかわる場合があります。)
利尿剤
利尿剤は、体内の余分な水分や塩分を尿として排出する薬です。むくみや息切れなどの症状を改善する効果があります。
カリウムなどの電解質のバランスに影響を与えることもあるため、定期的な血液検査が必要です。
ACE阻害薬(アンジオテンシン変換酵素阻害薬)/ARB(アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬)
血管を拡張させて血圧を下げることで、心臓の負担を軽減します。ACE阻害薬とARBは作用の仕組みは少し異なりますが同様の効果が期待できます。
β遮断薬
β遮断薬は心拍数を減らし、血圧を下げることで心臓の負担を軽減する薬です。ただし、急に服用を開始すると症状が一時的に悪化する可能性があるため、少量から始めて徐々に増量していきます。
ARNI(サクビトリルバルサルタン;エンレスト)
ARNIは比較的新しい心不全治療薬で、従来のACE阻害薬やARBよりも心不全の患者さんの症状悪化を予防する効果があるとされています。
ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬は、腎臓でアルドステロンの働きを阻害し、ナトリウム排出を促進して血圧を下げる効果があります。心臓肥大も抑制するため、高血圧と心不全の両方の治療に用いられます。
SGLT2阻害薬(フォシーガ、ジャディアンスなど)
SGLT2阻害薬は、元々は糖尿病の治療薬でしたが、近年、糖尿病の有無にかかわらず心不全の患者さんや腎不全の患者さんに効果があることがわかってきました。心不全の悪化の予防につながる効果が認められており、新しい心不全
治療薬として注目されています。
イバブラジン
イバブラジンは心拍数を減少させる薬で、心拍数が多い低心機能の心不全患者さんの場合に使用します。β遮断薬が使用できない患者さんや、β遮断薬を使用しても心拍数が十分に下がらない患者さんに適しています。
可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)刺激薬(ベルイシグアト;ベリキューボ)
sGC刺激薬には血管拡張作用があり、心臓や腎臓の機能を改善する効果が期待されています。標準的な心不全の治療を行っても症状が改善しない低心機能の心不全患者さんに対して使用を検討します。
心不全患者の塩分制限・
水分管理の重要性
 心不全の患者さんは体内の水分バランスが崩れやすく、余分な水分が体に溜まりやすい状態です。
心不全の患者さんは体内の水分バランスが崩れやすく、余分な水分が体に溜まりやすい状態です。
過剰な塩分摂取は水分貯留を促進し、むくみや息切れなどの症状を悪化させる可能性があるため、適切な塩分制限や水分管理を行うことで、心不全の症状コントロールや薬物治療の効果を高めることができます。
塩分制限
塩分は体内の水分量を調節する重要な役割を持っていますが、心不全では過剰な塩分が体内に水分を引き寄せ、むくみや息切れなどの症状につながるため、適切に制限する必要があります。
水分管理
心不全の患者さんは体内の水分バランスが崩れやすく、過剰な水分摂取は症状の悪化につながります。特に重症の心不全や腎機能障害を合併している場合は、水分摂取量の制限が必要になることがあります。