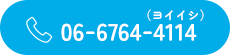- 骨粗鬆症は50歳以上の女性に
増加傾向!?骨粗鬆症について - 骨粗鬆症の症状(軽度・重度)
- 骨粗鬆症の原因・なりやすい人の特徴
- 骨粗鬆症の検査
- 骨粗鬆症の治療
- 骨粗鬆症予防に必要な栄養とは?
骨を強くする食事のポイント
骨粗鬆症は50歳以上の女性に
増加傾向!?骨粗鬆症について
 一般的に、骨密度は加齢とともに低下します。骨密度の低下には女性ホルモンの減少、腸でのカルシウム吸収力の低下、ビタミンD生成能力の衰え、食事量・運動量の減少などの様々な要因が関わっています。
一般的に、骨密度は加齢とともに低下します。骨密度の低下には女性ホルモンの減少、腸でのカルシウム吸収力の低下、ビタミンD生成能力の衰え、食事量・運動量の減少などの様々な要因が関わっています。
骨粗鬆症は男性より女性の方が発症リスクが高く、特に閉経を迎える更年期(50歳前後)以降は注意が必要です。加齢に伴う体の変化には避けられない部分もありますが、若いうちから適切な食事と運動習慣を心がけることで、骨密度の減少速度を抑えることは可能です。
骨粗鬆症の早期発見・早期治療のためにも、40歳を超えたら定期的な検査をおすすめします。まずは一度、大阪市の鶴橋駅前よしかわ内科へお気軽にご相談ください。
閉経と骨粗鬆症の関係
骨粗鬆症は女性に多い疾患で、患者さんの80%以上が女性と言われています。女性ホルモンの一種であるエストロゲンには、骨からのカルシウム流出を抑える働きがあります。
閉経を迎えてこのホルモンの分泌が減少すると、骨密度が急激に低下してしまうため、同年代の男性よりも早く骨が脆くなってしまいます。
骨代謝(骨の新陳代謝)
骨は一度形成されたら変化しないと思われがちですが、実は常に古い骨が壊され、新しい骨に生まれ変わる新陳代謝(骨改変)を繰り返しています。
健康な状態では、骨を壊す「骨吸収」と骨を作る「骨形成」のバランスが保たれているのですが、骨吸収が骨形成を上回ってしまうと、骨の内部がスカスカになって強度が低下します。これが骨粗鬆症で、脆くなった骨はわずかな衝撃でも骨折しやすくなります。
骨粗鬆症の症状(軽度・重度)
骨粗鬆症の怖いところは、自覚症状がないまま静かに進行することです。そのため「沈黙の疾患」とも呼ばれています。多くの場合、骨折して初めて骨粗鬆症に気づくことになります。以下のような症状が見られた場合は骨粗鬆症の可能性がありますので、骨折を防ぐために早急に治療を開始することが重要です。
軽度の骨粗鬆症の主な症状
- 立ち上がる時の背中や腰の痛み
- 重い物を持った際の背中や腰の痛み
- 背中や腰が曲がる
- 身長が縮む
など
重度の骨粗鬆症の主な症状
- 背中や腰の痛みで立てなくなる、寝込んでしまう
- 転倒などのわずかな衝撃で骨折する
- 背中や腰の曲がりが顕著になる
- 著しく身長が縮む
など
骨粗鬆症の原因・
なりやすい人の特徴
骨量減少の最大の原因は加齢ですが、以下のような複数の要素が絡み合って発症します。
- カルシウム摂取の不足
- 女性ホルモンの減少
- カルシウム調節機能の低下
また、卵巣摘出や糖尿病、ステロイド薬の長期使用、慢性肝障害などが原因で発症する「続発性骨粗鬆症」は、年齢や性別を問わず起こる可能性があります。
骨粗鬆症になりやすい人の特徴
喫煙
喫煙習慣がある方は、そうでない方と比べて骨粗鬆症のリスクが高まります。
過度なアルコール摂取
1日にビール中瓶2本または日本酒2合程度のアルコール摂取で、骨折リスクが上昇します。
低体重
体重が少ない方(低BMI)は、特に大腿骨の骨折を起こしやすくなります。
加齢
同じ骨密度でも、年齢が高いほど骨折リスクは増加します。
閉経
早い年齢で閉経した方や両側卵巣を摘出した方は、女性ホルモンの分泌がより少なくなるので、骨粗鬆症のリスクが高まります。
ステロイド服薬歴
ステロイド薬は、炎症や免疫反応を抑えるための治療薬です。しかし、ステロイドには副作用があるため、使用が長期に及ぶと骨密度を著しく低下させます。
遺伝
東アジア系の人は骨量が比較的少なく骨折しやすい傾向があります。また、家族に骨粗鬆症患者がいる場合もリスクが高くなります。
過去の骨折
脊椎、大腿骨、上腕骨、橈骨などの骨折歴がある方は、新たな骨折が発生しやすくなります。
カルシウム不足
食事からのカルシウム摂取量が少ないと、骨量低下のリスクが高まります。
運動不足
運動不足だと骨に適度な負荷がかからないため、徐々に脆くなっていきます。適切な運動は若年〜中年期では骨量増加に、高齢者では転倒予防に役立ちます。
骨粗鬆症の検査
骨粗鬆症の診断では、骨の量を測定する「骨密度検査」が用いられます。骨の単位面積あたりに含まれるカルシウムやリンなどのミネラル成分量を調べ、骨粗鬆症や骨折リスクを評価します。
主な骨密度測定法には、X線を用いる方法と超音波を用いる方法があります。
二重エネルギーX線吸収法(DXA)
2種類のX線を骨に照射して骨量を測定します。全身の骨を測定できますが、骨粗鬆症では特に腰椎や大腿骨頸部、手首などが主な測定部位となります。通常のレントゲン撮影より被ばく量が少なく、骨量測定法の中では最も精度が高い検査方法です。
MD法
手のX線撮影を行い、人差し指の付け根から手首までの骨(第二中手骨)の骨密度を測定します。アルミニウム板との濃度比較によって骨密度を評価する方法で、一般的なX線装置で実施できます。
定量的超音波測定法(QUS)
かかとの骨に超音波を当て、伝わる速度から骨の状態を調べます。放射線被ばくがなく、短時間で測定できるため、健康診断や骨粗鬆症検診などでよく利用されています。妊婦さんでも安全に検査が可能です。
骨粗鬆症の治療
骨粗鬆症の治療では、骨密度の低下を抑えて骨折を防ぐことが主な目的となります。治療の中心は薬物療法ですが、長年の食習慣や運動習慣も発症に深く関わっているため、併せて食事療法や運動療法も実施します。
薬物療法
 骨粗鬆症の治療薬には様々な種類があり、患者さんの状態に合わせた選択肢が広がっています。骨密度増加効果の高い薬や、服用頻度や剤型(錠剤、注射など)を工夫した使いやすい薬も登場しています。
骨粗鬆症の治療薬には様々な種類があり、患者さんの状態に合わせた選択肢が広がっています。骨密度増加効果の高い薬や、服用頻度や剤型(錠剤、注射など)を工夫した使いやすい薬も登場しています。
ただし、効果を十分に得るためには、薬の正しい使い方を守ることが重要です。服用のタイミングや注意点は薬によって異なりますので、医師や薬剤師の指示に従って服用してください。
(1) 骨吸収を抑制する薬
骨が壊される速度を抑える薬です。新しい骨を定着させやすくすることで、骨密度の高い骨を作ります。
主な薬
女性ホルモン製剤(エストロゲン)、ビスフォスフォネート製剤、SERM(塩酸ラロキシフェン、バゼドキシフェン酢酸塩)、カルシトニン製剤、デノスマブ など
(2) 骨の形成を促進する薬
新たな骨の形成を助ける薬です。骨形成と骨吸収のバランスが取れた状態を目指します。
主な薬
活性型ビタミンD3製剤、ビタミンK2製剤、テリパラチド(副甲状腺ホルモン)
(3) その他
丈夫な骨を作るために必要な栄養素を補充し、骨粗鬆症を予防します。
主な薬
カルシウム製剤、ビタミンD など
食事療法
 骨の形成に必要なカルシウム、ビタミンD、ビタミンKなどの栄養素を積極的に摂取することが大切です。特にカルシウムとビタミンDは、同時に摂ることで腸でのカルシウム吸収率が高まります。
骨の形成に必要なカルシウム、ビタミンD、ビタミンKなどの栄養素を積極的に摂取することが大切です。特にカルシウムとビタミンDは、同時に摂ることで腸でのカルシウム吸収率が高まります。
また、高齢になると食の好みの変化や小食傾向からタンパク質摂取が不足しがちです。タンパク質不足は骨密度低下を促進するため、意識して摂るようにしましょう。バランスの良い食事を規則正しく摂ることが、食事療法の基本です。
運動療法
 骨に負荷がかかる運動ほど骨を強くする効果があります。エアロビクスよりはバレーボール、さらに重量挙げのような高負荷の運動が骨強化に有効ですが、無理に激しい運動をする必要はありません。日常生活の中で無理なく取り入れられる運動を、医師と相談しながら実施していきましょう。
骨に負荷がかかる運動ほど骨を強くする効果があります。エアロビクスよりはバレーボール、さらに重量挙げのような高負荷の運動が骨強化に有効ですが、無理に激しい運動をする必要はありません。日常生活の中で無理なく取り入れられる運動を、医師と相談しながら実施していきましょう。
骨粗鬆症予防に必要な栄養とは?骨を強くする食事のポイント
骨に必要な栄養素
カルシウム
- 骨の主成分であり、骨形成を促進します
具体的な食品
乳製品(牛乳、チーズ、ヨーグルト)、小魚(イワシ、シラス)、大豆製品(豆腐、納豆)、緑黄色野菜(小松菜、ブロッコリー)など
ビタミンD
- 小腸でのカルシウム吸収を促進します
- 食事のほか、日光を浴びることで体内でも生成されます
具体的な食品
サンマなどの青魚、キノコ類(特に干しシイタケ)、卵黄など
ビタミンK
- 骨の質を高めるコラーゲンを増加させる働きがあります
- 緑黄色野菜に豊富に含まれています
具体的な食品
納豆、ほうれん草、ブロッコリーなど
その他
- マグネシウム:骨芽細胞に働きかけ、骨のカルシウム量を調節します。ナッツ類、海藻、豆類に多く含まれます
- タンパク質:不足すると骨密度の低下を助長します。肉、魚、卵、大豆製品が良い供給源です
- イソフラボン:女性ホルモンに似た作用があり、骨の破壊を抑えます。大豆製品に多く含まれます
- ビタミンB6、B12、葉酸:骨の強度を支えるコラーゲン形成に関わります
過剰摂取を避けた方が良い食品
リン
- カルシウムの吸収を阻害します
具体的な食品
清涼飲料水、加工食品、スナック菓子、インスタント食品
ナトリウム
- カルシウムの尿中排泄を促進します
- 塩分の多い食品(漬物、ラーメン、スナック菓子など)の摂りすぎに注意しましょう
具体的な食品
食塩など
カルシウム
- カルシウムの吸収を妨げます
- カフェイン含有飲料の摂取量に気をつけましょう
具体的な食品
コーヒー、紅茶、緑茶、コーラなど
アルコール
- カルシウムの吸収を妨げて尿中排泄を促進します
- ビタミンDの働きも阻害します
具体的な食品
ビール、日本酒、ワインなど