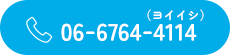鶴橋駅前よしかわ内科の特徴
①少しの体調変化でも
ご相談ください
 大阪市の鶴橋駅前よしかわ内科は、幅広く健康上のご相談に対応しております。
大阪市の鶴橋駅前よしかわ内科は、幅広く健康上のご相談に対応しております。
例えば「何となく調子が悪いのだけれど、どこが悪いのか、何科を受診していいのかわからない」というような曖昧な場合や、健康診断の結果を含む健康上の不安などについても、お気軽にご相談ください。
②地域の皆さんの
「かかりつけ医」です
 当院は、地域にお住まい・お勤めの皆さんのかかりつけ医を目指して、適切な医療を受けるための「総合案内」としての役割を担っております。
当院は、地域にお住まい・お勤めの皆さんのかかりつけ医を目指して、適切な医療を受けるための「総合案内」としての役割を担っております。
特に体調が優れない時に多くの患者さんが受診する内科では、あらゆる可能性を考えながら、幅広い視野から診察を行い、今の病状についてわかりやすくご説明し、いち早く快適な生活に戻れるよう治療を行います。
③必要に応じて適切な
医療機関をご紹介します
 当院は、近隣の医療機関や専門医と連携しておりますので、高度な医療や入院治療、手術が必要と判断された場合には適切な医療機関や専門医へのご紹介をいたします。
当院は、近隣の医療機関や専門医と連携しておりますので、高度な医療や入院治療、手術が必要と判断された場合には適切な医療機関や専門医へのご紹介をいたします。
内科で診療しているその他の疾患
内科は、以下のような病状や疾患のほか、生活習慣病や感染症など多くの疾患について診療します。
花粉症(アレルギー疾患)
スギ、ヒノキ、シラカンバ、ハンノキといった植物の花粉がアレルゲンとなり発症するアレルギー疾患です。体内に侵入した花粉に対して、免疫が過剰に反応することで、くしゃみ・鼻水・鼻づまり、目のかゆみなどの症状が引き起こされます。
花粉症の主な症状
- 連続したくしゃみ
- 水っぽい鼻水
- 鼻づまり
- 目のかゆみ、充血
- のど、耳の中のかゆみ
- 集中力の低下、だるさ
スギであれば2~4月、ヒノキであれば3~5月に、花粉の飛散が多くなります。アレルゲンとなる花粉が飛散している時期だけ、症状が続きます。
花粉症の検査・診断
症状の種類や悪化するタイミング、生活習慣などについて詳しくお伺いします。その上で、花粉・ハウスダストに関連する項目を調べる血液検査(特異IgE抗体検査)を行い、診断します。
花粉症の治療法
抗ヒスタミン薬、ロイコトリエン受容体拮抗薬などの内服薬、点鼻薬・点眼薬などを用いた薬物療法が中心となります。また、スギ花粉アレルギー(またはダニアレルギー)の根治治療を目指せる舌下免疫療法にも対応しております。
日常生活での花粉症対策
-
花粉情報を調べ、飛散の多い日には外出を控える
-
外出時にはマスク、ゴーグル、帽子などを着用する
-
帰宅時には花粉を払って入室する、すぐにうがい
-
洗顔をする(できればそのまま入浴する)
-
室内を換気する、空気清浄機を使用する
医療機関で行う治療とともに、上記のような花粉への対策を行うことも大切です。
その他のアレルギー疾患
花粉症以外にも、以下のようなアレルギー疾患に対応しております。
-
蕁麻疹…特定の食物、薬剤、ストレスなどを原因として皮膚にかゆみ・発疹が現れます。
-
通年性アレルギー性鼻炎…ハウスダストを原因として、年間を通してくしゃみ・鼻水・鼻づまり症状が続きます。
- アトピー性皮膚炎、気管支喘息の診断・治療にも対応します。お気軽にご相談ください。
貧血(鉄欠乏性貧血、
悪性貧血など)
貧血は、酸素を運ぶ役割を持つ赤血球やヘモグロビンが不足し、全身へ必要な酸素を十分に供給できなくなる疾患です。倦怠感・めまい・動悸が続く場合は、重症化の可能性もあるため、早めの受診が大切です。
甲状腺疾患
(バセドウ病、橋本病など)
甲状腺疾患は、体内のホルモン分泌や代謝を調節する甲状腺の機能が低下・過剰してしまう疾患です。
甲状腺ホルモンが過剰に分泌されると動悸や発汗、体重減少を引き起こし、甲状腺機能が低下するとむくみ・寒がりなどの症状が現れます。
膠原病(関節リウマチ、全身性エリテマトーデスなど)
膠原病は、自己免疫が自身の関節・皮膚・血管などの組織を標的として攻撃するために、全身に炎症を引き起こす疾患の総称です。膠原病の1つである関節リウマチは朝の関節痛などが特徴で、全身性エリテマトーデスは発熱・皮膚の発疹・腎障害を伴うことがあります。
慢性疲労症候群
慢性疲労症候群は、極度の疲労が積み重なった末に、十分な休息をとっても改善せず、集中力の低下・筋肉痛・微熱などの症状が長期的に続く疾患です。
不定愁訴(原因不明の体調不良、めまい、倦怠感など)
不定愁訴は特定の病気に罹っている可能性はないものの、慢性的な倦怠感・めまい・頭痛・胃の不快感などの症状が続く状態を指します。
自律神経の乱れ・ストレス・ホルモンバランスの変化が関与していることが多く、生活習慣の見直しやストレス管理が重要です。
神経疾患(自律神経
失調症、片頭痛など)
自律神経失調症は、交感神経と副交感神経のバランスが崩れることで、全身のだるさ・冷え・不眠などの症状が現れる疾患です。片頭痛は血管の拡張により起こる頭痛で、眩しい光・大きな音・気圧の変化などが発症原因になることが特徴です。
内科の検査
当院では、病気の診断や健康状態の把握のために様々な検査を行います。

血液検査
血液検査は、貧血や炎症、肝機能・腎機能の異常、ホルモンの血中濃度などを調べます。
尿検査
尿検査は腎臓や膀胱の異常、糖尿病の有無を確認するのに効果的です。
心電図検査
心電図検査は心臓疾患や原因の特定に役立てられ、不整脈や心臓の負担を評価するために行います。
その他の検査
他にも呼吸機能検査やアレルギー検査、自律神経機能検査なども行い、総合的に診断します。症状や疑われる病気に応じて、適切な検査を組み合わせ、早期発見と治療につなげます。
内科の治療
当院の内科では、病気の種類や症状に応じて以下のように適切な治療を行います。
薬物療法
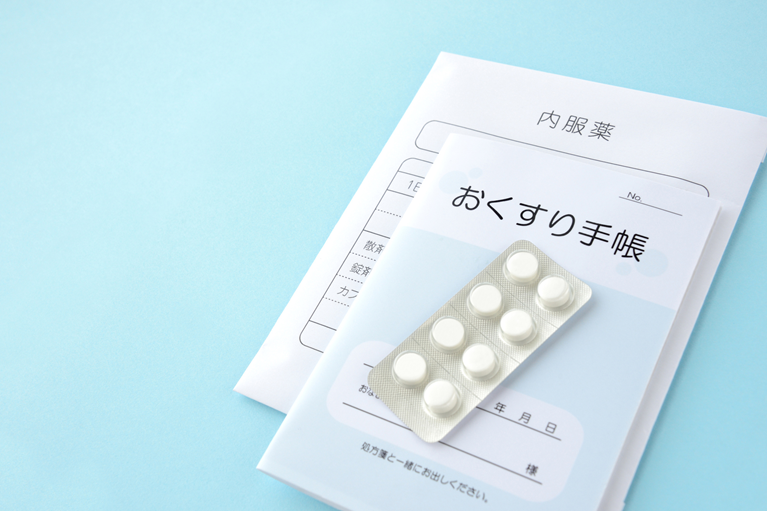 薬物療法では、高血圧や糖尿病、感染症、アレルギー疾患などに対し、降圧薬、血糖降下薬、抗生剤、抗アレルギー薬などを使用します。
薬物療法では、高血圧や糖尿病、感染症、アレルギー疾患などに対し、降圧薬、血糖降下薬、抗生剤、抗アレルギー薬などを使用します。
生活習慣の改善と工夫
慢性疲労症候群や不定愁訴などの場合は生活習慣の改善も重要で、食事指導や運動療法などを通じて病気の進行を防ぎます。
ホルモン補充療法
甲状腺疾患などホルモンバランスの異常がある場合は、ホルモン補充療法を行うこともあります。
ホルモン補充療法には副作用が見受けられることもあるため、状態に合わせて適宜補充量を調節していきます。
循環器内科で診療している
その他の疾患
当院は、以下のような心臓や血管に関連する疾患を含め、血流や血圧の異常に関わる疾患も診療します。
高血圧症(本態性高血圧、
二次性高血圧)
高血圧症は、慢性的な血圧上昇により動脈へ負担がかかる状態です。治療が遅れると、徐々に病状が進行し心疾患や脳梗塞などのリスクを高めます。
低血圧症(起立性低血圧、
神経調節性失神)
低血圧症は、血管収縮の遅れや自律神経の乱れなどが原因で、急激な血圧下降を引き起こすことがあります。これにより立ちくらみやめまい、失神を引き起こします。
動脈硬化症(閉塞性動脈硬化症、大動脈瘤など)
動脈硬化症は、動脈の内側にコレステロールが蓄積し、血管が狭くなることで血流が悪化する疾患です。
病状が進行すると引き起こされるものに閉塞性動脈硬化症や大動脈瘤があり、下肢のしびれや組織の壊疽、動脈瘤の破裂といった重篤なリスクを有します。
深部静脈血栓症(DVT)
深部静脈血栓症は、長時間にわたって座り続けている場合や手術後などの姿勢保持において血液が固まりやすくなり、足の深部静脈に血栓ができる疾患です。
急に姿勢を変えたり、立ち上がったりした際に、足の血栓が肺に移動すると肺塞栓症を引き起こす危険があります。
肺高血圧症
肺高血圧症は、肺の血管の圧力が異常に高くなり、息切れや疲れやすさを引き起こす疾患です。進行すると心臓や血管に負担がかかり心不全などの発症リスクが高まるため、早期診断と治療が重要です。
末梢動脈疾患(PAD)
末梢動脈疾患は、閉塞性動脈硬化症やバージャー病などの総称で、手足の動脈が狭くなり、血流が低下する疾患です。症状は歩行時の痛みやしびれ、冷感が特徴で、重症化すると潰瘍や壊死に至ることもあります。
心筋炎・心膜炎
心筋炎・心膜炎は、ウイルス感染や自己免疫の異常などにより、心臓の筋肉や膜に炎症が起こる疾患です。
発症すると胸の痛みや息苦しさ、むくみ、発熱などを伴います。
これらの病気は、血管内の流れの問題や閉塞により深刻な合併症を引き起こすことがあるため、正確な診断と適切な医療介入が不可欠です。心拍の乱れ、呼吸困難、体の一部の浮腫、または胸部の不快感などの症状がございましたら、そのままにせずに一度当院へご相談ください。
循環器内科の検査
当院で行っている循環器内科の検査は、下記の通りです。
- 心電図
- レントゲン検査
- 心臓超音波検査(心エコー検査)
- 24時間ホルター心電図検査
- ABI(足関節上腕血圧比)検査
また当院は通常の内科診療も行っているため、循環器以外の疾患が見つかった場合も診療可能です。
循環器内科の治療
当院で行う循環器内科の治療について、以下の4つをご紹介します。
薬物療法
 高血圧などの循環器症状の進行を抑えるために、最もよく用いられるのが薬物療法です。
高血圧などの循環器症状の進行を抑えるために、最もよく用いられるのが薬物療法です。
例えば、不整脈には心臓のリズムを整える薬、狭心症には血管拡張薬などと、病状に応じた薬剤を選択し、適切な用量を内服することで症状の改善と進行抑制を見込めます。
食事療法・運動療法
特に循環器疾患は、生活習慣の影響を受けていることがあり、食事や運動の工夫を行うことで薬物療法との相乗効果が現れやすくなります。
食事療法は高血圧を誘発する食材の制限、禁酒、禁煙、減塩などに取り組みましょう。運動療法は、軽い有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、階段昇降など)を習慣づけて行うことが大事です。
心臓カテーテル治療
心臓カテーテル治療とは、手首もしくは足の付け根の動脈から太さ2mmの柔らかい管(カテーテル)を挿入後にバルーン(風船)やステントを広げて、冠動脈の狭い部分や閉塞した部位を拡張する治療です。
この治療が必要と判断された場合は、当院より提携している医療機関をご紹介します。
外科的手術
循環器疾患において最後に検討される治療方法が、外科的手術です。
全身麻酔のもと、疾患に応じて冠動脈バイパス手術、弁形成術、弁置換術などが選択されます。
この治療が必要と判断された場合は、当院より提携している医療機関をご紹介します。